

私は5カ月に及ぶサバイバル留学を終え、日本へ帰国しました。帰国した際、羽田空港の景色は出国前と比べて、少し変わって見えたような気がしました。5カ月間、周りに日本人が1人もいない初めての環境で生活したことで、少し自分が成長したかのように感じたのだと思います。私は英語の教員を目指しているため、英語の国で同じく英語教員を目指す学生たちと学びを深めた経験は、とても有意義なものでした。
ノーサンブリア大学で履修した科目は言語心理学と認知言語学で、福大で私が学んでいる生成文法とは全く異なる分野でした。しかし、異なるからこそ、両方の視点を学び比較できるようになったことで、それぞれの特徴がより際立って見えるようになったと感じています。
また、ヨーロッパ諸国出身のルームメイトたちとの生活においても、自分の捉え方との違いを学ぶことがありました。ある日、私は夕食を作りたかったのですが、ルームメイトの1人がキッチンでパーティを開く準備をしていたので、料理をするのをやめました。しかし後になってルームメイトに聞いてみると、「他の人がなにかをやっていたとしても、自分がしたいことがあれば遠慮せずにしてもいい」というようなことを言われたことがあります。また、他のルームメイトからは、「日本に行ってはみたいけれど、ルールが厳しそう」と言われたこともあります。確かに、その時の私は日本での生活と同じように、周りの雰囲気や規律に合わせていたのかもしれません。
しかし、それが欠点かといえば、そうとも思いません。東京に帰って最初に気づいたのは、道がきれいなことでした。これは、多くの人が公共の場を汚さず、規律を守り、きれいに使おうとする意識を持っているからこそ実現できるのだと感じました。少なくとも、道の美しさに感動した私にとっては、周りに合わせることも良い面があると感じられます。
結局のところ、どちらかの考えが絶対によいということはありえないと実感させられました。もちろんヨーロッパにいたときは、自分を主張するというヨーロッパでの考え方に染まるよう努めていましたが、そうであるからこその利点や欠点があり、日本の考え方にも同様に当てはまると感じています。
このように今回の留学では、異なる考え方を比較する場面が多くありました。しかし、そこに優劣をつけることもありませんでした。むしろ、言語学の領域にしても、文化的な考え方の違いにしても、全く異なるものを比較することによって、お互いが際立つようにも感じられます。もうそろそろ、イギリスの友人が日本を訪れる予定ですが、日本の考え方の良さを伝えられるよう、自分の言葉を準備しながら彼を待ちたいと思っています。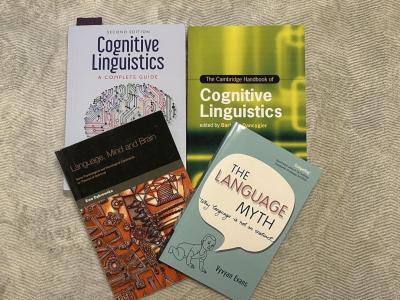
▲テキスト
▲認知言語学のMimi先生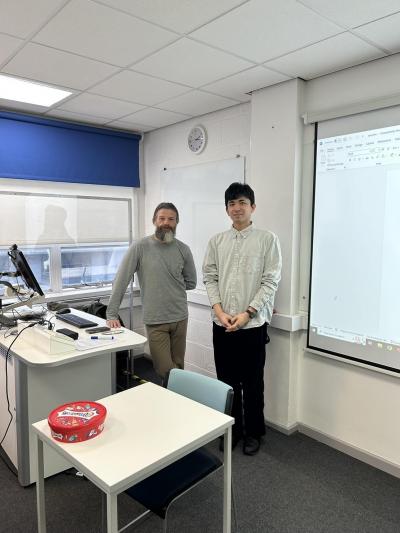
▲言語心理学のJames先生
▲福大つながりでドイツ
▲夜のニューカッスル
▲福大に留学したHarleyと彼のルームメイト
▲寮の友人たちとのパーティー